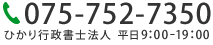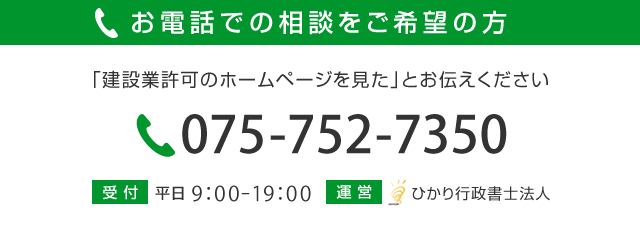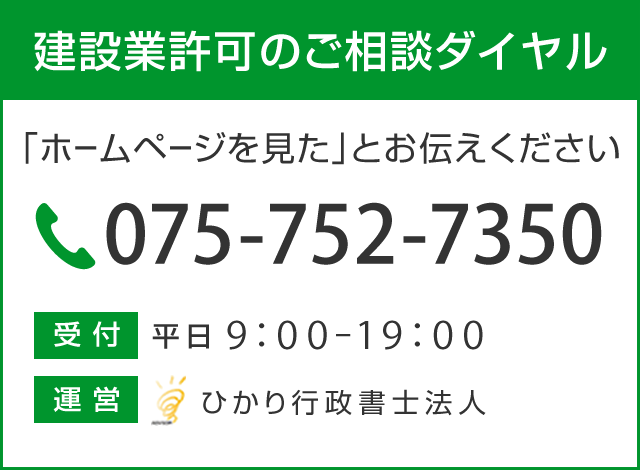令和2年10月1日施行の改正建設業法によって、「経営業務の管理責任者」から「経営業務の管理体制・適正な経営体制」という制度への変更がなされました。
これまでは「役員個人の経営経験」に基づき「経営業務管理責任者」となることができましたが、改正建設業法の施工後は「役員個人の経営経験」にあわせて「組織としての経営経験」によっても、「経営業務管理責任者」になることができるようになりました。
経営業務の管理体制・適正な経営体制について
新たな制度の下で経営業務管理責任者になるために、二つのパターンから選択できることになっています。
- ひとりで「経営業務管理責任者」を設置する場合
- 組織(複数人)で「経営業務管理責任者」を設置する場合
ひとりで経営業務管理責任者を設置する場合
これまでと同様に、建設業に関する経営経験が必要となります。
改正により要件緩和となった点としては、実際に従事していた業種については経営経験5年、従事していない業種については経営経験6年というしばりがなくなり、5年間の建設業の経営経験があれば、建設業の経験の経験に関しては業種は問わないこととなっており、この点はかなりの緩和措置となっています。
要件をみたすための経営経験は次のとおりとなっています。
| (イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当していること | |
|---|---|
| (イ)-1 | 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理者としての経験を有する者(登記簿上の取締役や個人事業主など) |
| (イ)-2 | 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者(執行役員など) |
| (イ)-3 | 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者(支店長・工事部長など) |
常勤役員等とは、法人の場合は常勤の役員(取締役など)、個人事業主の場合は本人又は支配人のことをいいます。
(イ)-1 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理者としての経験を有する者
「登記簿上の取締役」や「個人事業主」として5年以上、建設業を経営していた経験がある場合に「経営業務管理責任者」となることができます。
改正建設業施行前は、従事していた建設業の業種については5年以上、従事していない建設業の業種については6年以上の経営経験が必要とされていましたが、改正法施行後は、5年の経営経験があれば、実際に従事していない業種についても5年以上の経営経験があればよいとされています。
(イ)-2 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、どういったものになるのでしょうか?
これは、「執行役員」という地位になります。
会社法上の取締役ではないため登記簿には載っていないけれど、会社内部で「執行役員」に任命されていることが必要となります。
その任命されていた期間が5年以上あれば、「経営業務管理責任者」の要件を満たすこととなります。
執行役員は、会社で自由に任命することができますが、建設業許可申請のしばりとして、「取締役会設置会社」で任命されたことが必要とされています。
建設業許可ガイドラインにおいては、「取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する」と定義されています。
執行役員の要件は次のとおりとなります。
- 取締役会設置会社で任命されたこと
- 代表取締役・取締役に次ぐ地位で建設業に関する業務執行を行っていること
役員からの権限委任などを証明するために、定款、会社の組織図、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役会議事録、辞令などで内容が判断されることとなります。
(イ)-3 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
役員に次ぐ地位として、経営業務を補佐した経験が6年以上ある場合、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。
補佐した経験とは、役員に次ぐ地位にあるような役職となりますので、支店長や工事部長などの役職についており、建設業に関する権限を持つ職位が必要となるでしょう。
6年以上の経営補佐経験についても、以前は従事している業種のみに認められていましたが、改正法施行後は、従事しない業種についても認められることとなりました。
これまでは、経営補佐経験を証明するために、6年分の各業種ごとの証明書類(請負契約書・注文書請書など)の提示が必要でしたが、1つの業種を証明することで足りることとなりました。
たとえば、専任技術者となる一級建築施工管理技士が在籍する会社で、例えば一業種でも経営補佐経験を証明できれば、資格で取得できる全業種の建設業許可が取得できることになります。
会社組織として経営業務管理責任者を設置する場合
経営経験がある役員と補佐する従業員の合わせ技で経営業務管理責任者を設置する方法となります。
建設業に関わる役員経験5年を満たすことができないが、一定以上はあるような場合に、この方法を利用することになります。
| (ロ) 常勤役員等のうち一人が次の(ロ)-1または(ロ)-2のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、次のA、B及びCに該当する者をそれぞれ置くものであること。なお、A、B及びCは一人が複数の経験を兼ねることを可能とする。 | |
|---|---|
| (ロ)-1建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理または業務運営を担当する者に限る)における経験を有する者 | A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 |
| B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 | |
| C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者 | |
| (ロ)-2 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者 | A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 |
| B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 | |
| C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者 | |
(ロ)-1か(ロ)-2 に該当する方が主役です。
- (ロ)-1建設業の役員経験が2年以上あり、それに加えて建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者
- (ロ)-2建設業の役員経験が2年以上あり、それに加えて建設業以外の役員等の経験を3年以上有する者
主役となる役員は、建設業の役員経験2年以上は必須となります。
それに加えて(ロ)-1か2の後段の要件を満たすことができるかどうかを確認することになります。
そのうえで、主役を補佐するABCの「直接補佐者」三名を設置することで「経営業務管理責任者」の要件を満たすこととなります。
- A:申請会社において5年以上の財務管理の経験を有する者
- B:申請会社において5年以上の労務管理の経験を有する者
- C:申請会社において5年以上の運営業務の経験を有する者
ABCの「直接補佐者」は同一人物が兼務することが可能ですし、5年の補佐期間も重複することができます。
最低人数は二人から申請が可能となることになります。
改正建設業法のポイント(経営業務の管理体制)まとめ
改正建設業法の経営業務管理体制の解説はいかがだったでしょうか?
改正法が施行される前には、経営業務管理責任者の要件自体がなくなると噂されるなど胸ときめいていましたが、そこまでとはなりませんでした。
であっても、要件としては緩和されたことは確かですので、今後は建設会社の事業承継や相続などについても、いくぶんかは柔軟に対応できるようになったといえると思います。
建設業許可についてのお問い合せ
ひかり行政書士法人では、建設業許可についてのご相談や建設業許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
京都府・滋賀県の建設業許可についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。
その他の許認可申請について
その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。